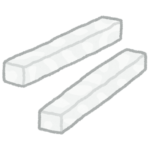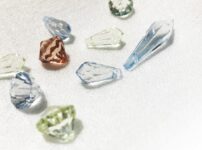ボイラー水管理において計測項目の一つにシリカがあります。水の硬度が高い地域でボイラーを使用する場合は、シリカは注意すべきポイントの一つになります。
今回はシリカ計測器の原理について解説します。
シリカとは
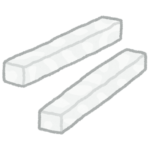
シリカとは二酸化ケイ素やケイ酸とも呼ばれる物質のことで、自然界には石英という鉱物として多く存在します。また乾燥剤でお馴染みのシリカゲルは、文字通りシリカをゲル化したものです。
欧州の国々ではミネラル豊富な硬水であることが知られていますが、一方で日本の水は花崗岩や石英の影響でシリカが多く含まれています。
産業分野でも水道水や地下水を使うので、シリカ濃度には気をつける必要があります。特にボイラーやクーリングタワーなど水が凝縮されるような用途では、シリカ濃度が上がりやすいです。
測定時に使用される単位は、mg/Lです。例えばボイラーに関してJIS規格では、10MPa以下では2mg/L以下(蒸気中のシリカ濃度が0.02mg/L以下)が望ましいとされています。
シリカ測定器の原理


計測にはモリブデンブルー法(モリブデン青吸光光度法)という、昔から用いられる方法が使われていることが多いので、この測定原理の解説をしようと思います。
シリカは酸性環境下で、モリブデン塩酸と反応して錯体を生成します。これに酸(アスコルビン酸など)を添加し還元させると青色(モリブデンブルー)になり、これに600-800nmの波長の光を当てて吸光度を測定するというものです。
試薬を使った化学反応を用いるため、単に電流値を測るわけではないので連続測定できませんが、機械的に15分間隔などで計測することができる機器はあります。
計測器には連続使用を目的にした大型の装置もあれば、ポケットに入るサイズのものもあります。用途に合わせてご検討ください。
シリカ測定器の注意点
取扱説明書通りに計測を行えば問題ないかと思いますが、注意点としては2点挙げられます。
計測時間がかかる
サンプルを試薬に添加してからすぐに結果が出るわけではなく、反応して青色が出るのに数分かかります。キットや装置によって必要時間は変わるので、マニュアルに従ってください。
とはいえ、多くの機器には自動カウントダウン機能がついているようなので、あまり気にしなくても良いかと思います。
セルやチューブの洗浄が必要
ポータブルの場合は毎回、据置で連続稼働の装置の場合は定期的に、装置内の洗浄が必要です。
吸光度測定はガラス製の「セル」と呼ばれる入れ物にサンプルを流し、光を当てて吸光度を測定するため、セルが汚れていると正しく計測できません。純水を使ってマニュアル通りに洗浄してください。
連続稼働タイプの場合は、試薬や洗浄液のボトルを一定期間(例えばあるメーカーの装置なら60日間)ごとに入れ替える必要があり、その際に洗浄を行うことになります。
まとめ
- シリカは二酸化ケイ素やケイ酸とも呼ばれる物質
- 水に含まれるシリカは鉱物に由来することが多く、水が濃縮される用途では対策が必要
- 吸光度を測るガラス製の検出部をきれいに保つ必要がある
ボイラー水質管理に重要な機器ですので、正しい方法で使用・管理を行ってください。

計測機器
2024/7/7
【環境】発電所に尿素水があるのはなぜ?目的について解説
発電所では、エネルギーの安定供給と環境保護の両立が求められます。 その中で、排出ガスの管理は非常に重要な課題です。特に火力発電所では、燃焼によって窒素酸化物(NOx)が生成され、これは大気汚染の原因となります。 発電所に尿素水があるのは、このNOxを削減するためです。本記事では、尿素水の役割とその効果について詳しく説明します。 尿素水とは 尿素水は、尿素(CO(NH2)2)を水に溶かした液体です。 この液体は、SCR(選択触媒還元)装置で利用されることで知られています。SCR装置は、排ガス中のNOxを無害 ...
ReadMore

計測機器
2022/3/3
【計測】濁度の測定方法は?どの測定原理がいいの?
工場で使う飲料水や、製品の原料溶液、処理する工場排水など、産業分野において水質を正しく測定することは重要です。 指標の1つでもある濁度は、「単位が曖昧で、よくわからない」という方も多いのではないでしょうか。今回は、濁度の単位と測定原理の違いについて、解説していきたいと思います。 濁度とは 濁度とは字の通り「水の濁り」を表します。しかし、例えば導電率(S/m)のような明確な単位はなく、単に「度」と言われます。これは、濁度が基準の溶液に対してどの程度、試料が濁っているかを示す単位であるからです。 基準となる標 ...
ReadMore

計測機器
2021/8/30
【計測機器】光高温計の原理、メリット、放射温度計との違いは?
計測機器の原理について知ることは、生産・運転状況の正しい理解や、トラブル時の対応に生かされると思います。 今回は温度計の一種、光高温計の原理やメリット、デメリットについて解説します。光高温計は放射温度計に分類されますが、高温の被測定物にしか使われない特殊な温度計になります。 光高温計とは 光高温計とは、熱放射を測定することで温度に換算する放射温度計の一種です。 英語ではOptical pyrometerと呼ばれています。赤外線を利用するタイプの放射温度計(体温計としての利用で話題となり、品薄になりましたね ...
ReadMore
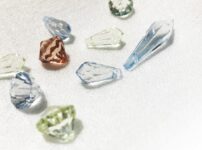
計測機器
2021/8/30
【計測機器】水晶温度計の原理、メリット・デメリットは?
温度の計測機器について、今回は水晶温度計をとりあげます。 水晶と聞くと宝石の一種というイメージですが一体どのような仕組みで温度を測定するのでしょうか? 水晶温度計の原理やメリット、デメリットについて解説したいと思います。 水晶温度計とは 水晶温度計とは、水晶振動子や水晶発振子と呼ばれる部品を使用した温度計です。クオーツ温度計とも呼ばれます。 測温センサの組み込まれたプローブと、周波数を測定し温度に変換する計測器によって構成されます。 水晶温度計の原理 原理を説明するために、段階を追って解説をしていきます。 ...
ReadMore

計測機器
2021/8/30
【計測機器】シリカって何?シリカ測定器の原理と注意点
ボイラー水管理において計測項目の一つにシリカがあります。水の硬度が高い地域でボイラーを使用する場合は、シリカは注意すべきポイントの一つになります。 今回はシリカ計測器の原理について解説します。 シリカとは シリカとは二酸化ケイ素やケイ酸とも呼ばれる物質のことで、自然界には石英という鉱物として多く存在します。また乾燥剤でお馴染みのシリカゲルは、文字通りシリカをゲル化したものです。 欧州の国々ではミネラル豊富な硬水であることが知られていますが、一方で日本の水は花崗岩や石英の影響でシリカが多く含まれています。 ...
ReadMore