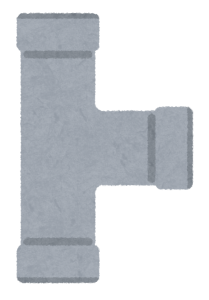最近の工場では、新設の段階からステンレスの配管を採用することが多いように思います。
以前は、配管の材質は基本的に鉄だったので数年使用すれば錆が出てきて、それが要因でバルブなどを何度交換しても固着してしまうなんてことがあったかとおもいます。
ステンレスにすれば、鉄に比べて錆びにくいので、長期的な運用を考えればステンレス配管にしておくほうがいいということになります。
では、ステンレス配管はいい事ずくめなのでしょうか?今回は、ステンレス配管にすることによるデメリットについてまとめてみたいと思います。
こちらの記事は動画でも解説しているので、動画の方がいいという方はこちらもどうぞ。
1. ステンレス配管とは?
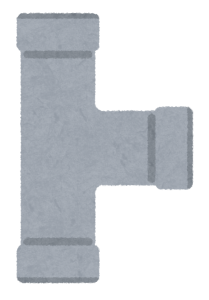
ステンレス配管とは、言葉の通りステンレスでできた配管のことです。
ステンレスは鉄とニッケルとクロムの合金で、自身のまわりに不動態と呼ばれる薄い酸化被膜を作ることで、鉄に比べて酸化しにくい性質があります。
ただ、あくまで錆びにくいというだけで絶対に錆びないわけではないので注意が必要です。
2. ステンレス配管のデメリット
新設の段階から標準で設置されるステンレス配管ですが、次のようなデメリットがあります。
2-1. 値段が高い
まず一番に挙げられるのが、ステンレス配管は値段が高いことです。
モノタロウ(外部リンク)で検索してみると、目安の金額が出てきました。
- ステンレス配管 25A 4m 11000円
- 鉄配管 25A 4m 4390円
ステンレス配管は鉄配管に比べ、約2.5倍の値段がします。
短距離であれば気にならないかもしれませんが、大型の設備になるとコストに大きな差が出てきてしまいます。
2-2. 熱膨張が大きい
ステンレス配管は鉄配管に比べ、熱膨張しやすいという性質があります。
そのため、配管を施工する際はUベントやフレキシブルチューブなどで熱膨張を吸収してやらなければいけません。
膨張率を鉄配管と同じように設計すると、フランジが外れたり、配管に亀裂が入るなどのトラブルが発生してしまいます。
2-3. 熱伝導率が低い
金属の熱伝導は、内部を自由に動き回る自由電子によって変化します。
ステンレスは鉄に比べ、ニッケルやクロムが入っているため、自由電子の動きを妨げ、熱伝導率が下がります。
輸送配管では放熱が多少下がるためメリットになりますが、熱交換器などに使用する場合は注意が必要です。
同じ交換熱量で設計した場合は、伝熱面積を多少大きく取る必要があります。
2-4. 焼け付きが発生しやすい
ステンレスは、ボルトを占めるときなどに無理な方向に力が加わると金属同士が溶着する「焼け付き」が発生しやすいという特徴があります。
これを工事関係者の間では「かじる」や「がじる」といいますが、焼け付きが発生してしまうとボルトが取れなくなり、最悪の場合新品と交換しないといけなくなります。
ステンレスの製品を扱う場合は、上手くボルトが入らなかった際に無理に力を掛けず丁寧に扱う必要があります。
3. まとめ
ステンレス配管のデメリットは
- 値段が高い
- 熱膨張が大きい
- 熱伝導率が低い
- 焼け付きが発生しやすい
配管ではありませんが、、ステンレスは粘り気があり、加工が難しいという特徴もあります。
錆びないということで非常に利用が増えてきたステンレス配管ですが、これらを注意しながら扱う必要がありそうです。
コストを考えると、錆がどうしても発生しやすい水配管のみステンレス配管にするなんてこともありかもしれませんね。

配管
2024/7/7
【配管】ラプチャーディスクを設置する目的、安全弁との違いは?
産業施設やプラントの運用において、安全性を保つための圧力管理は非常に重要です。 過剰な圧力が発生すると、設備の損傷や事故の原因となり得るため、適切な圧力解放装置が必要です。 ラプチャーディスクと安全弁はその代表的な例ですが、それぞれの特徴や設置目的には明確な違いがあります。本記事では、ラプチャーディスクの設置目的と安全弁との違いについて解説します。 ラプチャーディスクとは ラプチャーディスクは、過圧保護を目的とした安全装置の一種です。主にプロセス産業や化学工場など、高圧の流体を取り扱う場所で使用されます。 ...
ReadMore

配管
2024/7/5
【配管】ストレーナに差圧計をつけるのはなぜ。設置するメリットは?
ストレーナは、流体システムにおいて異物や不純物を取り除くために使用される重要な機器です。 その中で、ストレーナに差圧計が設置されているのを見たことがある方もいるのではないでしょうか。本記事では、ストレーナに差圧計をつける理由について解説します。 ストレーナとは ストレーナは、流体(液体や気体)の中に含まれる固形物や異物を捕捉するための装置です。 流体がストレーナを通過する際に、フィルターが異物を取り除き、クリーンな流体だけが下流に送られます。これにより、ポンプやバルブ、熱交換器などの重要な機器が異物による ...
ReadMore

配管
2022/7/31
【配管】フランジ規格FFとRFの違い、使い分けは?
バルブや配管を接続するフランジにはJIS10Kなどの後ろにFFやRFという種別が記載されています。 低圧ではFFとRFでどちらを使っても問題ない場面が多いので使い分けが良く分からないという方も多いのではないでしょうか? この記事では、フランジの座面形状を表すFFとRFの違いについて解説します。 FFとRFの違い FF FFはFlat Face(フラットフェイス)の略で上の図のようにガスケットの座面を全面に仕上げたものを言います。主にJIS10K、JIS20K、JPI150、JPI300などの低圧で使用され ...
ReadMore

配管
2022/7/31
【配管】バッファータンクの役割とは?設置するメリットは
給排水系統や空気系統では負荷変動を抑えるためにバッファータンクが良く用いられます。 この記事では排水系統などで良く利用されるバッファータンクについて解説します。 バッファータンクとは バッファータンクとは気体や液体を一時的に貯留させるためのタンクです。レシーバータンクとも呼ばれ、給排水系統や空気系統などに設置されます。 バッファータンクを設けることで、設備のイニシャルコスト低減や工場の安定性を向上させることが出来、大きければ大きいほど変動許容率が上がります。 バッファータンクの役割 バッファータンクの役割 ...
ReadMore

配管
2022/7/31
【配管】バケットストレーナーとは何か、メリットデメリットを解説
ポンプや制御弁など重要な機器を保護するためにはストレーナーは必須です。 この記事では大口径の配管に良く採用されているバケットストレーナーとは何か、また、メリットデメリットについて解説します。 バケットストレーナーとは バケットストレーナーはバケット状のメッシュにて流体内の異物を取り除くための機器です。小口径で良く利用されるY型ストレーナに比べると大口径で利用されることが多い機器です。 内部のバケットは上部のカバーを取り外すことで取り出すことができ、定期的に洗浄を行うことで目詰まりなどを防止します。上部のカ ...
ReadMore