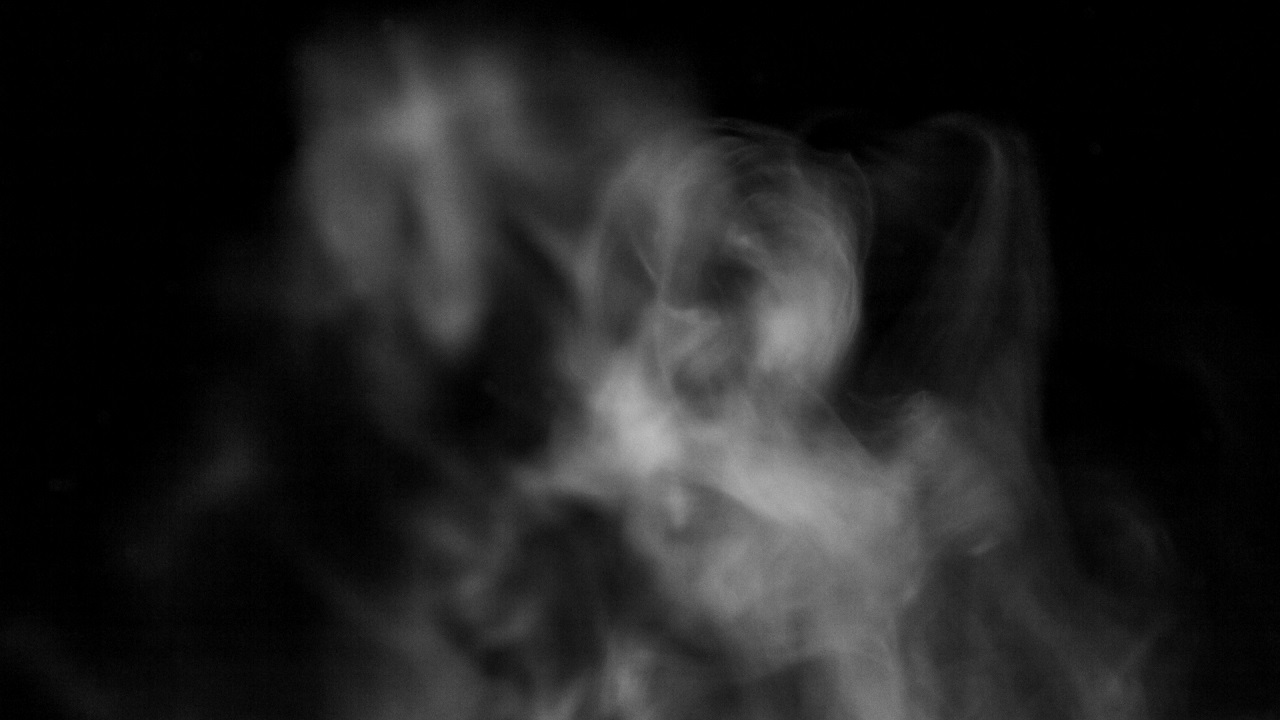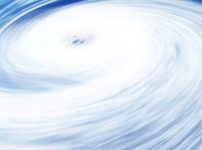流量計の種類や測定原理によっては、他のデータによる補正が必要なケースがあります。
今回は蒸気流量計の補正の必要有無について、解説します。
こちらの記事は動画でも解説しているので、動画の方がいいという方はこちらもどうぞ。
蒸気流量計の補正とは?
蒸気の計測を行う流量計にはいくつかの原理があります。
差圧式、渦式、電磁式などがメジャーな型式と言えます。ここの原理については過去の記事でまとめていますので、ぜひご覧ください。
-

【流量計】差圧式流量計って何?どんな仕組みか詳しく解説してみた
続きを見る
-

【流量計】カルマン渦って何?原理や活用法について
続きを見る
-

【流量計】超音波式と電磁式の違いって何?
続きを見る
どのタイプも体積を測定するタイプの流量計です。質量を測定するコリオリ式流量計は蒸気には対応していません。
さて、蒸気という気体は温度によって密度が異なることが知られています。例えば100℃の蒸気は約600g/m3なのに対し、180℃の蒸気は約5100g/m3の密度です。
同じ体積でも、密度変化により重さが変わるため、質量で蒸気を測定するためには温度による補正が必要となります。
言うまでもありませんが、蒸気のコスト計算は、燃料代だけでなく水の使用量も関係するため、蒸気も質量計算する必要があります。
実際には、流体の体積を測る測定部の他に、温度を測定する熱電対などが流量計に付属していることが多いです。もしくは流量計の近くに温度計を設置します。
2つのデータを、PLCなどの計算機内で蒸気表の補正式に当てはめた計算値、つまり蒸気質量が出力されます。
余談ではありますが、なぜ蒸気は補正を気にする必要があるのでしょうか?
他のガスの使用とは異なり、多くの場合蒸気は飽和状態で用いられます。そのため、温度変化による圧力変化、つまり密度変化の変動が大きいです。
密度の変化影響を受けない(小さい)種類の蒸気として、過熱蒸気があります。こちらを読んでいただければ、飽和状態とそれ以外の気体の性質の違いが理解できるかと思います。
-

【ボイラー】過熱蒸気をつくる過熱器の目的、用途は?
続きを見る
補正機能がないとどうなる?
温度による補正を使用しないまま蒸気流量計を使っていると、正しく使用量を測ることができません。
流量計の初期設定で、蒸気の温度もしくは圧力を設定するはずですが、その値より実際には大きい温度の蒸気が流れていると流量が過少に計測され、小さい温度だと過大に計測してしまうことになります。
流量計を設置している場所の温度(圧力)変化が大きい場合には、補正機能を正しく使う必要があると言えます。
蒸気温度が10℃変わると、蒸気の密度は1m3あたり1kg前後変わるため、質量計算した際には大きな違いが出ます(温度によって変化率が異なります、詳しくは蒸気表をご確認ください)。
一方で常に一定の温度の場所、例えば蒸気のメイン配管の場合には圧力変動が小さいと考えられるため、補正機能への設備投資は避けてもよいと言えます。
まとめ
- 蒸気は温度が変わると密度も大きく変わる
- 温度変化が大きい場所には流量計の温度補正が必要
蒸気流量計を設置している場所ごとに、必要か不要か判断するのがよいでしょう。

流量計
2022/12/22
【流量計】瞬時流量と積算流量の違い、使い分けは?
流量計には様々な型式がありますが、その中でも大きく分けて瞬時流量を示すものと積算流量を示すものの2通りがあります。 この記事では流量計の瞬時流量と積算流量の違いについて解説します。 瞬時流量とは 瞬時流量とはその瞬間に流れている流体の量を表す指標で単位はkg/h、ton/h、L/hなどで表されます。流量計からの信号の種類は4-20mAなどの電流信号とする場合が多いです。 主に工場やプラントで流量を監視したり、制御する場合は瞬時流量が用いられることがほとんどです。制御盤と接続する場合はセンサー電源を共用させ ...
ReadMore

流量計
2021/8/30
【流量計】蒸気流量計の使い方、補正はなぜ必要?
流量計の種類や測定原理によっては、他のデータによる補正が必要なケースがあります。 今回は蒸気流量計の補正の必要有無について、解説します。 こちらの記事は動画でも解説しているので、動画の方がいいという方はこちらもどうぞ。 蒸気流量計の補正とは? 蒸気の計測を行う流量計にはいくつかの原理があります。 差圧式、渦式、電磁式などがメジャーな型式と言えます。ここの原理については過去の記事でまとめていますので、ぜひご覧ください。 どのタイプも体積を測定するタイプの流量計です。質量を測定するコリオリ式流量計は蒸気には対 ...
ReadMore

流量計
2021/8/30
【流量計】静電容量式流量計ってどんな原理?電磁流量計との違いは?
今回は流量計の中でも、静電容量式というタイプの仕組みと用途について解説します。 静電容量式流量計とは? 静電容量式流量計を検索してみると「電磁流量計」のサイトがよく出てきました。 実は静電容量式流量計は、電磁流量計の1種です。何が違うのかというと静電容量式は、計測部の電極が配管の外にあるため液体と電極が直接触れない非接触型という点です。詳しくご説明します。 まず、静電容量とは何を指す言葉なのでしょうか。これは電気容量とも言われるそうですが、どれくらい電荷(静電気の量)を蓄えられるかを表しています。 導電体 ...
ReadMore
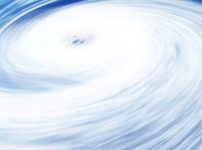
流量計
2021/8/30
【流量計】コリオリ流量計のメリット、デメリットについて解説!
流量計解説シリーズをいくつか続けてきましたが、今回はコリオリ流量計です。 業界によってはあまり見かけることはないかもしれませんが、面白い仕組みをしていますのでコリオリ流量計について解説していきたいと思います。 コリオリ流量計とは? 構造としては、流体が二股で平行に並んだ細いU字配管(フローチューブ)を通り、再び1本の配管に戻るという形状をしています。(1本の構造のものもあります) 2つのU字管内を流体が流れると、細い配管をねじ曲げようとする力が2つのU字間に対し逆方向に働きます。配管のねじれ角度を計測する ...
ReadMore

流量計
2021/8/30
【流量計】容積式流量計って何?どんな仕組みか詳しく解説してみた
流量計について調べたときに、歯車が2つ回る構造のものを見たことがありませんか? 今回はいくつかある流量計の型式の中の一つ、容積式流量計について詳しく解説します。 容積式流量計とは? 容積式流量計には、流量検出部に楕円状の歯車が2つ設置されています。 図で言うと、左から右に流体が流れることで歯車が回り、歯車上部分と下部分を流体が交互に流れていきます。 なぜ容積式と呼ぶかですが、升(ます)がよく例えに用いられます。水やお米を図るイメージをしていただきたいのですが、升で何リットル、何合と計りますよね。容積式流量 ...
ReadMore