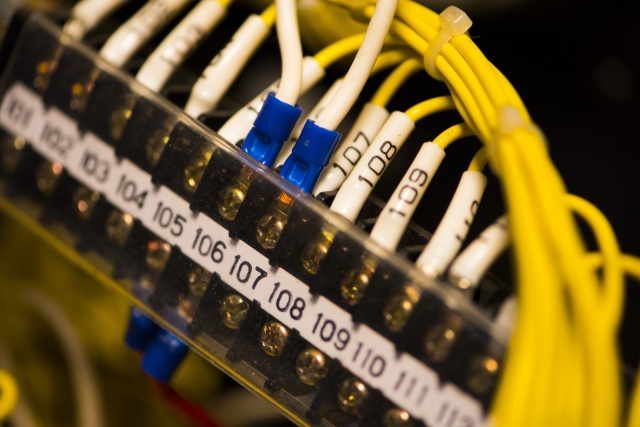電気機器を扱っていると「ヒューズが飛んだ!」なんてことを聞いたことがあるのではないでしょうか?
最近ではヒューズを使うことはほとんどありませんが、いまだに古い工場や家屋ではブレーカーではなくヒューズが使われていることもあるようです。今回は「ヒューズが飛ぶ」とはどういうことかについて詳しく解説します。
ヒューズとは
ヒューズとは、電気回路の保護装置の一種であり、過電流が流れると自身が溶断することで回路を遮断し、他の部品や機器を守る役割を果たします。一般的に、ヒューズは金属製の細いワイヤやストリップで構成されており、通常の動作時には電流を通過させるが、過剰な電流が流れるとその熱によって溶ける仕組みになっています。この動作により、過負荷や短絡による電気火災や機器の損傷を防止します。
ヒューズの主要な用途は、家庭用電化製品、車両、工業機械、電子機器などの電気回路の保護です。例えば、家庭内の電化製品が故障し過電流が発生した場合、ヒューズが溶断することで火災のリスクを低減します。また、自動車では、電気系統に過電流が流れるとヒューズが溶断し、車両の主要な電気部品を保護します。
ヒューズは、一度溶断すると再利用できないため、新しいものに交換する必要があります。この点で、過電流が頻繁に発生する環境では、ヒューズの管理と交換が重要となります。最近では、再使用可能なブレーカやリセット可能な保護装置も普及していますが、ヒューズのシンプルで確実な保護性能から依然として広く利用されています。
ヒューズが飛ぶとは?
「ヒューズが飛ぶ」とは、ヒューズに容量以上の電流が流れることで内蔵している合金部品が溶けて切れてしまった状態のことを言います。
ヒューズはブレーカーと同じ目的で、装置を過電流から保護する役割があります。ヒューズが飛ぶことによって、過電流による機器の発火や焼損などを防いでいます。
ヒューズに使われる合金としては、いわゆるはんだ付けに利用するような鉛、スズ、ビスマス、アンチモン、インジウム、カドミウムなどを混ぜたものが一般的です。ヒューズに一定以上の電流が流れることでジュール熱が発生し、金属部分が溶けて回路が切れます。
こちらの動画でヒューズが飛ぶ瞬間を見ることができます。
ヒューズが飛ぶ原因
ヒューズが飛ぶ原因としては次のようなものが考えられます。
- 過電流
- 短絡
- 過負荷
- 老朽化や劣化
- 選定ミス
- 電圧の変動
- 周囲環境
それぞれについて解説します。
過電流
過電流は、回路に流れる電流が設計された範囲を超える現象で、ヒューズが飛ぶ主要な原因の一つです。
過電流は、短絡や過負荷、電気機器の故障などによって引き起こされます。過電流が発生すると、ヒューズは過熱し、溶断することで回路を保護します。過電流を防ぐためには、電流が適切に流れるように回路設計を行うことが重要です。また、定期的なメンテナンスや点検を行い、過電流の原因となる問題を早期に発見して対処することも大切です。
短絡
短絡(ショートサーキット)は、電気回路内で正極と負極が直接接触する現象です。
これにより、非常に大きな電流が一瞬で流れ、ヒューズが即座に溶断します。短絡の原因には、配線の不良や絶縁の劣化が含まれます。特に古い電気設備や配線が劣化している場合、短絡が発生しやすくなります。
短絡を防ぐためには、定期的な配線の点検やメンテナンスが必要で、絶縁テープの交換や配線の整理も効果的です。短絡が発生すると、回路全体に深刻なダメージを与える可能性があるため、早期発見と対応が重要です。
過負荷
過負荷は、回路に接続されている機器が一度に多くの電力を消費する状態を指します。
これにより、回路に流れる電流がヒューズの定格電流を超え、ヒューズが溶断します。過負荷の一般的な原因としては、複数の高消費電力機器を同時に使用することが挙げられます。
例えば、家庭で複数の大型家電を同じコンセントに接続すると、過負荷が発生しやすくなります。過負荷を防ぐためには、電力消費量を分散させることが重要です。適切な配電と、必要に応じた電源の増設が効果的です。
-

【ポンプ】電流値は何で決まる?高い時と低い時の違いは?
続きを見る
老朽化や劣化
ヒューズ自体や配線が長期間使用されると、老朽化や劣化が進行します。
これにより、ヒューズが通常の電流でも溶断しやすくなります。特に高温多湿な環境では、劣化が加速される傾向があります。老朽化や劣化を防ぐためには、定期的な点検とメンテナンスが不可欠です。
古いヒューズや劣化した配線は早期に交換し、正常な動作を維持することが重要です。また、保管や使用環境を適切に管理し、劣化を遅らせる努力も必要です。
選定ミス
ヒューズの選定ミスも、ヒューズが飛ぶ原因となります。
回路の定格電流や電圧に適合しないヒューズを使用すると、適正な保護ができず、過電流が発生しやすくなります。適切なヒューズを選ぶためには、使用する機器や回路の特性をよく理解し、定格電流や電圧に適合したヒューズを選定することが重要です。
電圧の変動
電圧の変動もヒューズが飛ぶ原因の一つです。
電源供給が不安定な場合、電圧の急激な変動によって過電流が発生し、ヒューズが溶断します。特に、古い建物や電源設備が劣化している場合にこの問題が顕著になります。
電圧の変動を防ぐためには、電源設備の定期的な点検とメンテナンスが必要です。また、電圧安定装置(スタビライザー)の導入も効果的です。安定した電源供給を維持することで、ヒューズが飛ぶリスクを低減できます。
周囲環境
ヒューズが設置されている周囲環境も、その動作に影響を与えることがあります。
高温や湿度、振動などの環境要因がヒューズに負担をかけ、誤動作を引き起こすことがあります。例えば、工場や発電所などの過酷な環境では、特に注意が必要です。周囲環境がヒューズに与える影響を最小限に抑えるためには、適切な保護カバーの使用や、環境に応じたヒューズの選定が重要です。また、設置場所の環境管理を徹底し、過酷な条件を避けることも大切です。
ヒューズが使われなくなった理由
最近ではヒューズはほとんど利用されていません。ヒューズが使用されなくなった理由としては以下のようなものがあげられます。
ブレーカーの普及
ブレーカーの普及は、ヒューズが使われなくなった大きな理由の一つです。
ブレーカーは、過電流や短絡が発生した際に自動的に回路を遮断し、手動でリセットするだけで再利用が可能です。これにより、ヒューズのように溶断後に新しいものに交換する手間が省けます。
さらに、ブレーカーには過電流保護だけでなく、漏電保護機能を備えたものも多く、より総合的な安全性を提供します。この利便性と多機能性が、ブレーカーの普及を促進し、結果としてヒューズの使用が減少しました。
-

【制御盤】NFBとELBの違い、使い分けは?
続きを見る
経済性
経済性の観点からも、ブレーカーはヒューズに勝ります。
ヒューズは一度溶断すると再利用できないため、過電流が発生するたびに新しいヒューズを購入し、交換する必要があります。一方、ブレーカーは過電流や短絡が発生した際にトリップするだけで、リセットすれば再使用が可能です。
これにより、長期的に見てコスト効率が非常に高くなります。特に、頻繁に過電流が発生する環境では、ブレーカーの経済的な利点が顕著に現れます。また、交換の手間や時間も省けるため、メンテナンスコストも削減できます。
技術の進歩
技術の進歩も、ヒューズが使われなくなった理由の一つです。
現代の電気設備や機器は、高度な電子制御システムを搭載しており、過電流や短絡のリスクを低減しています。これにより、従来のヒューズに依存する必要が少なくなりました。また、新しいブレーカー技術は、より高い感度と正確さで異常を検知し、迅速に対応することが可能です。
さらに、スマートブレーカーの登場により、リモートでの監視や制御が可能となり、電力管理が一層効率的になっています。技術の進化により、ブレーカーはますます高度化し、安全性と利便性が向上する一方で、ヒューズの役割は減少しつつあります。
まとめ
- ヒューズは過電流が流れると自身が溶断することで回路を遮断し、他の部品や機器を守る役割
- ヒューズが飛ぶとは過電流で合金が溶けて切れること
- ヒューズが飛ぶ原因はショート、過負荷、漏電等
- ヒューズは使われずブレーカーが使われている
スイッチ操作を行う配線用遮断器のことを、三菱電機の呼称で「ノーヒューズブレーカー」なんて呼びますが、これはヒューズの入っていないブレーカーという意味です。
「ヒューズが飛ぶ」という言葉を聞くことはこれから少なくなっていきそうですね。